寒天
天草が干してあった。
よく水洗いし、甲殻類やゴミを手で一つ一つ取って干す。
お酢を数滴、ことこと煮て布巾で濾して、冷やせば100%天草の寒天。
黒蜜をかければほっぺたがおちる。
磯のごちそうだ。
Eddie Woul’d go(エディならいったさ)
ハワイライフガードでもあるエディー。
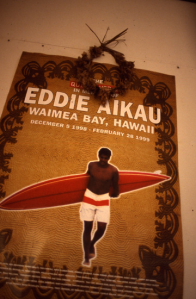
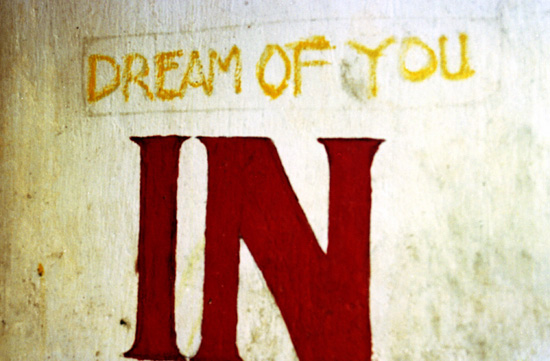



何を見ても新鮮で、わくわくした。


1995年頃のバリ島のウブド。

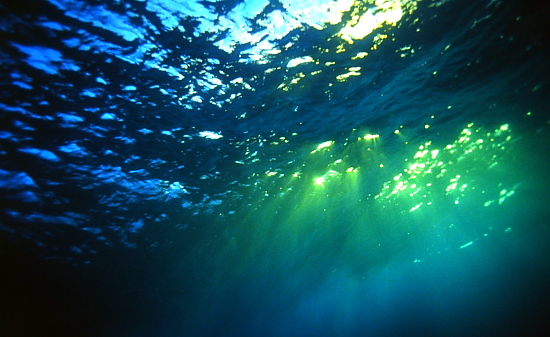
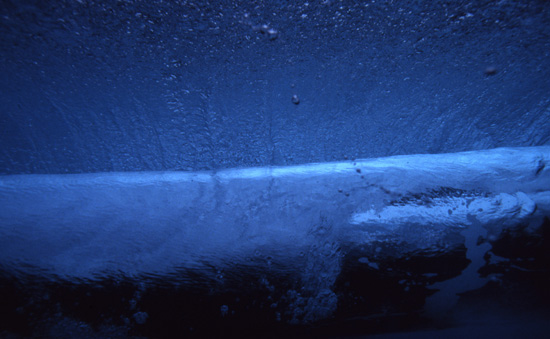

ごく自然にあるものは、曲線を選ぶ。
明け方ポートポレスビーについた。
首都ポートモレスビーから国内線で2時間程で、インドネシアの国境近くの海の村へ、極上の波とまだ見ぬ世界へ向かう。
蚊を媒介とするマラリア原虫用。
前後もあわせ16粒毎日一つ飲み込む。
新しく便利な物とは
パプアニューギニアへ行きます。
太古の地球と海とチューニングできたら、うれしく思います。
3月に又ご報告します。
宿 www.vanimosurflodge.com/
パプアニューギニア政府観光局 http://pngtourism.jp/
地図を助手席に広げマカハへ。
古き良きローカリズムが残る場所だと聞いていた。
たしかにノースとは異なりなんだか、穏やか。
古いピックアップトラックが風景と人の暮らしに溶け込んでいた。





 でっkおt
でっkおt



朝起きると、スパニッシュ系の見知らぬ短パンの角刈りが、



