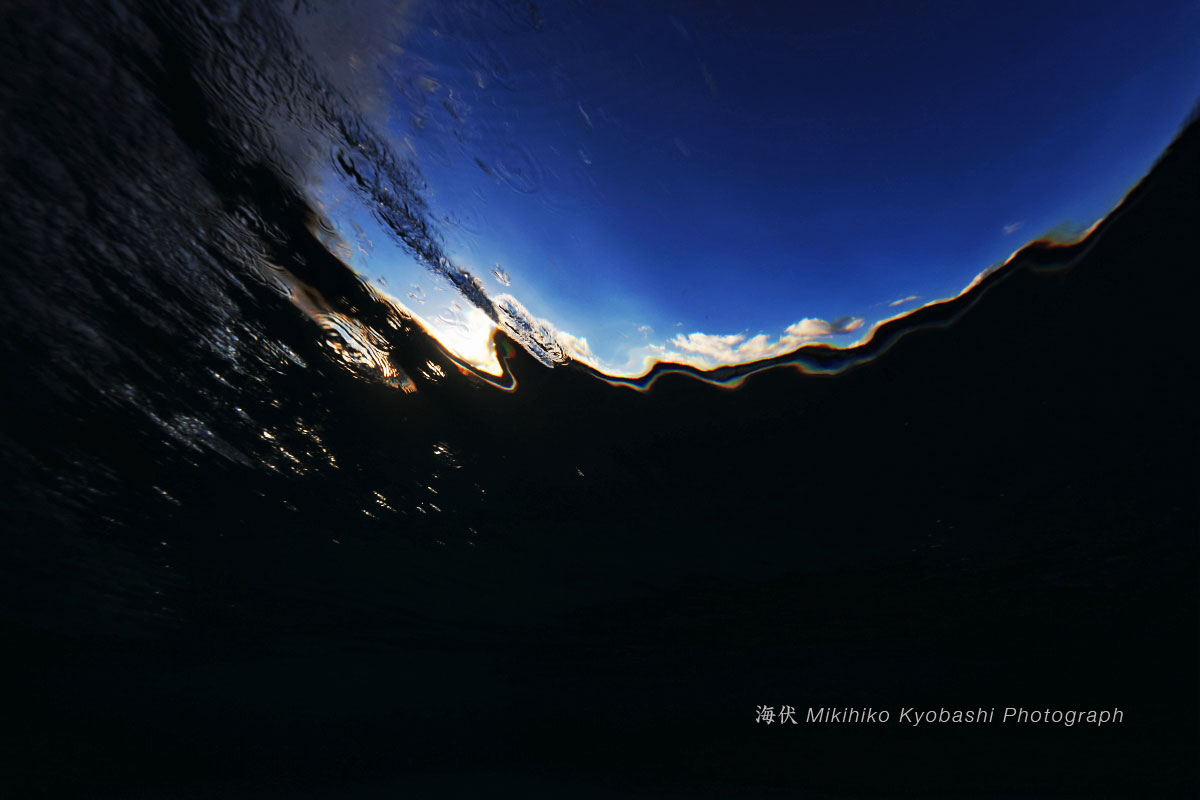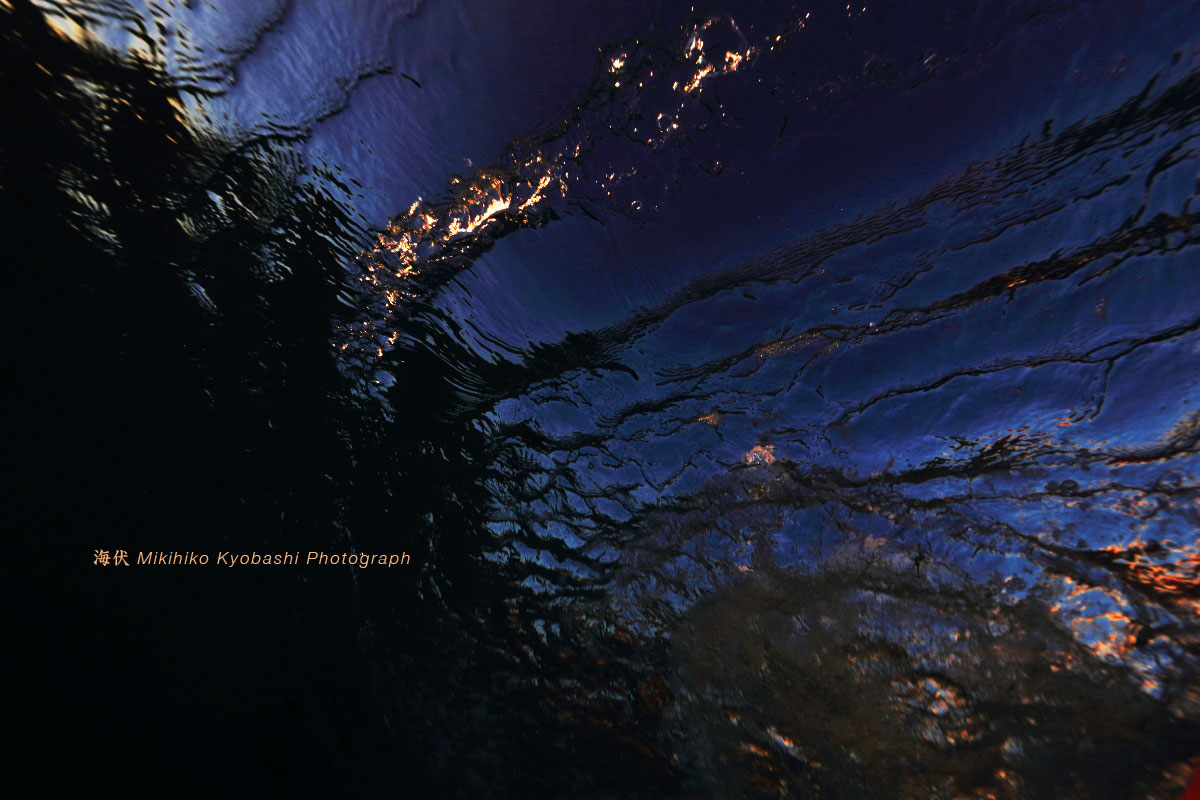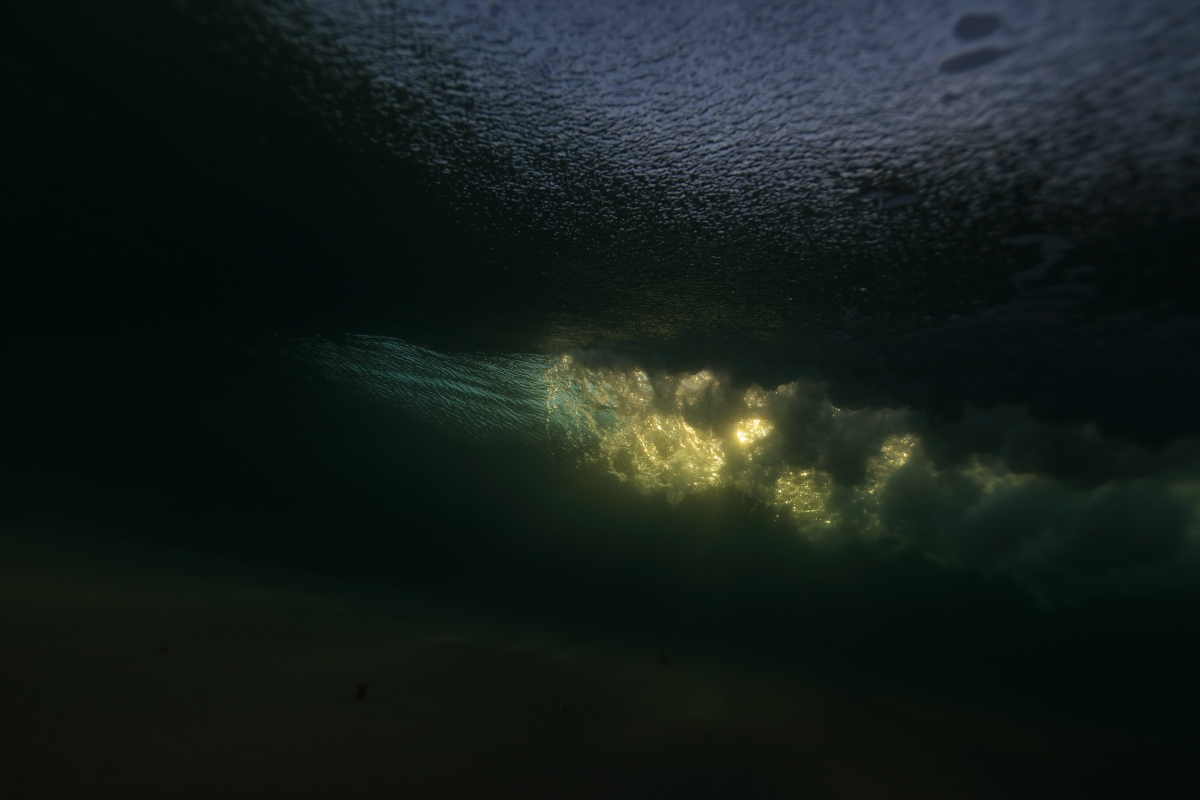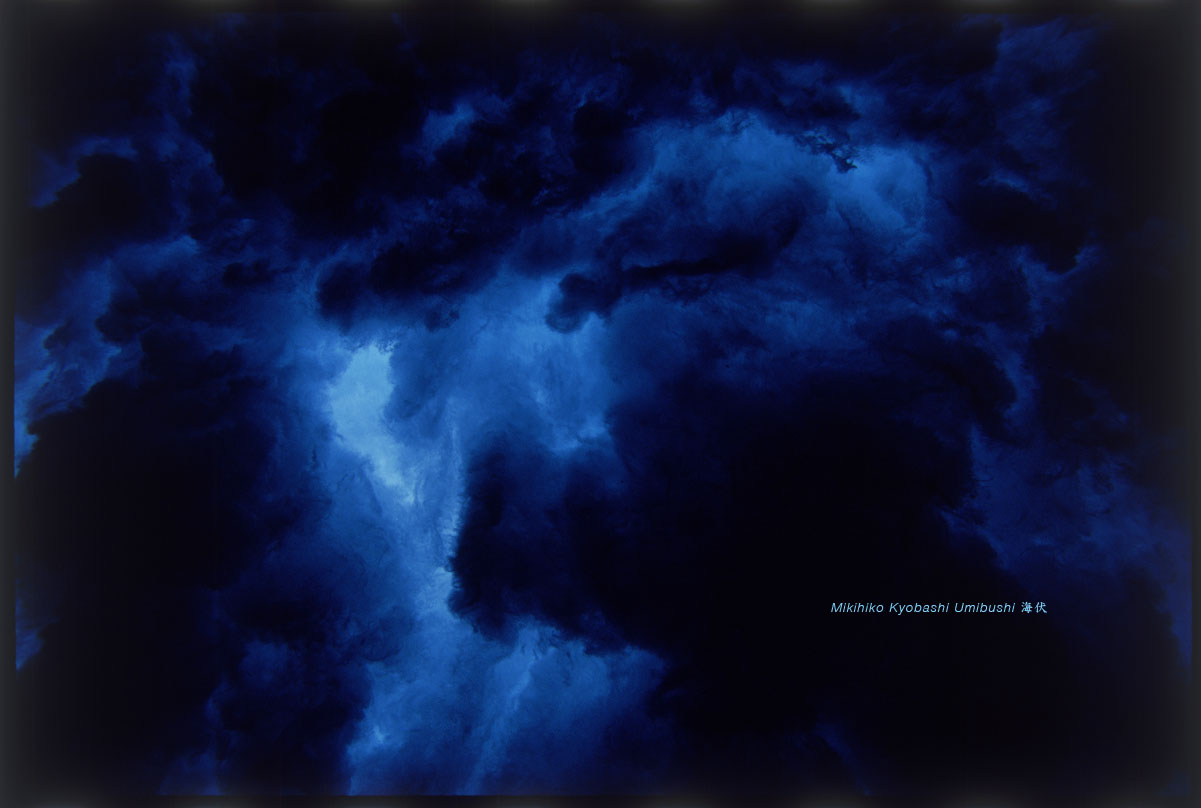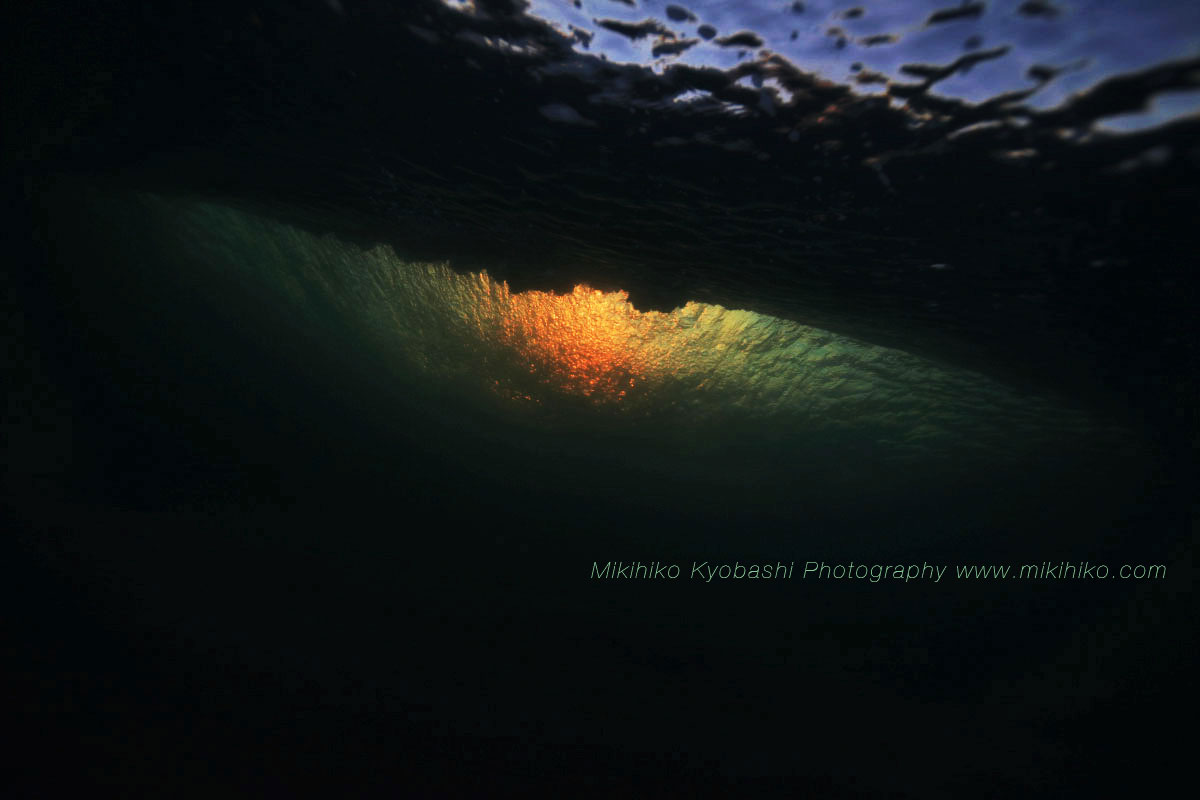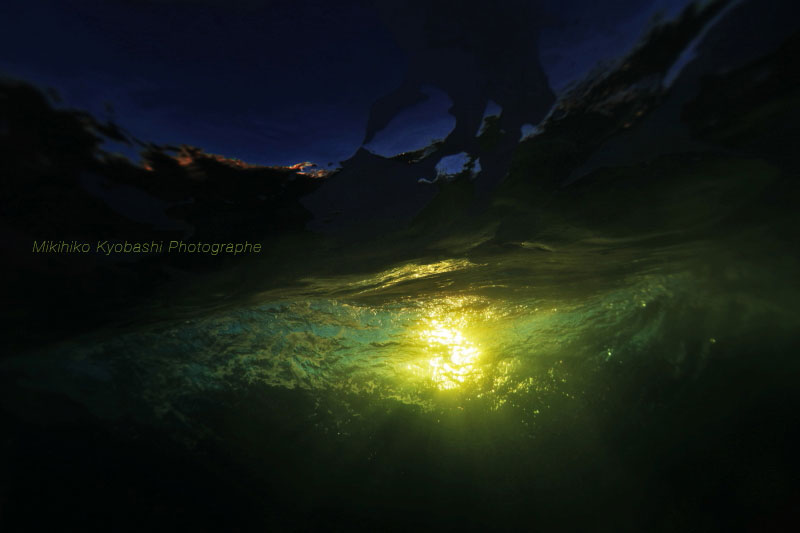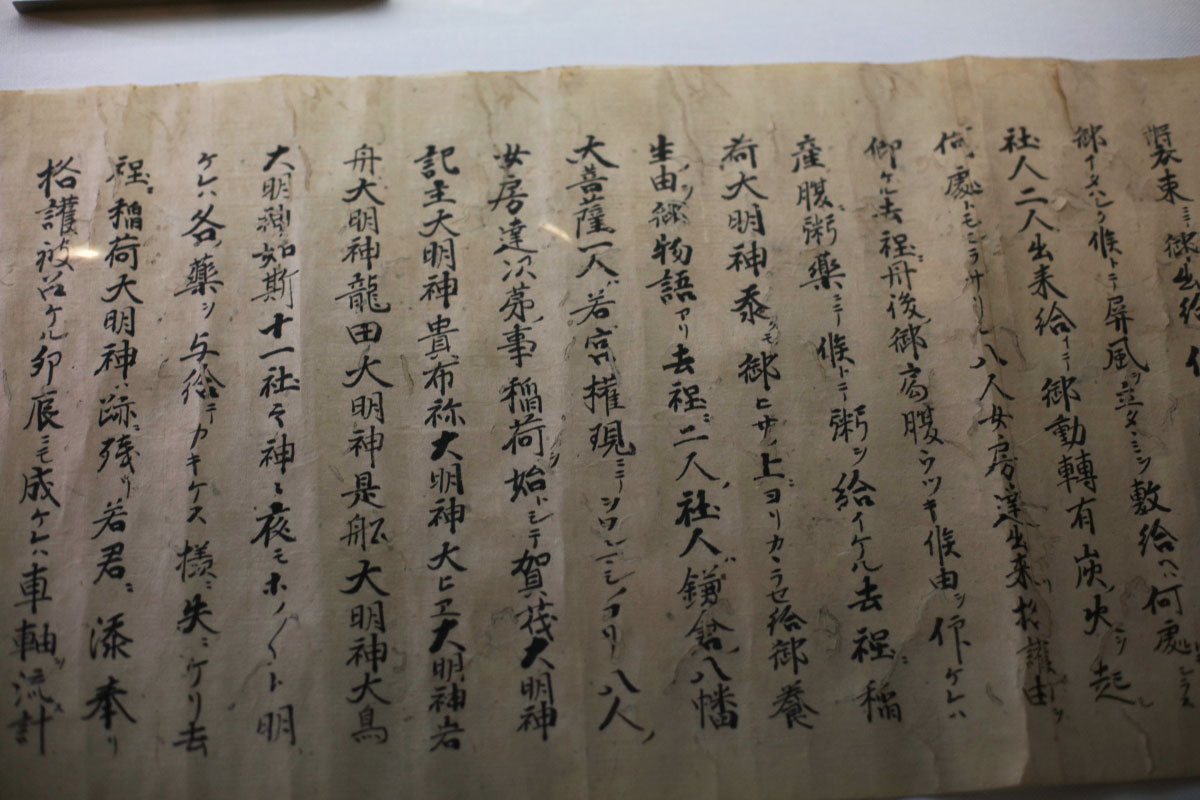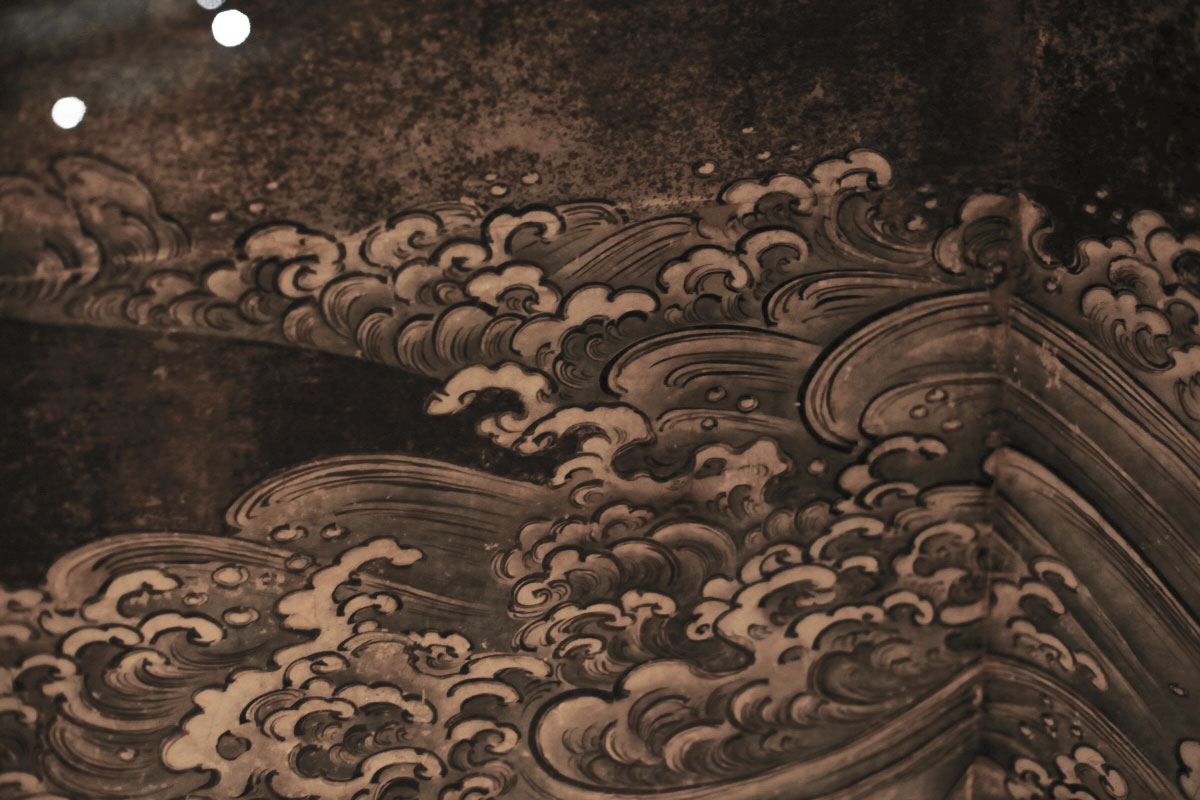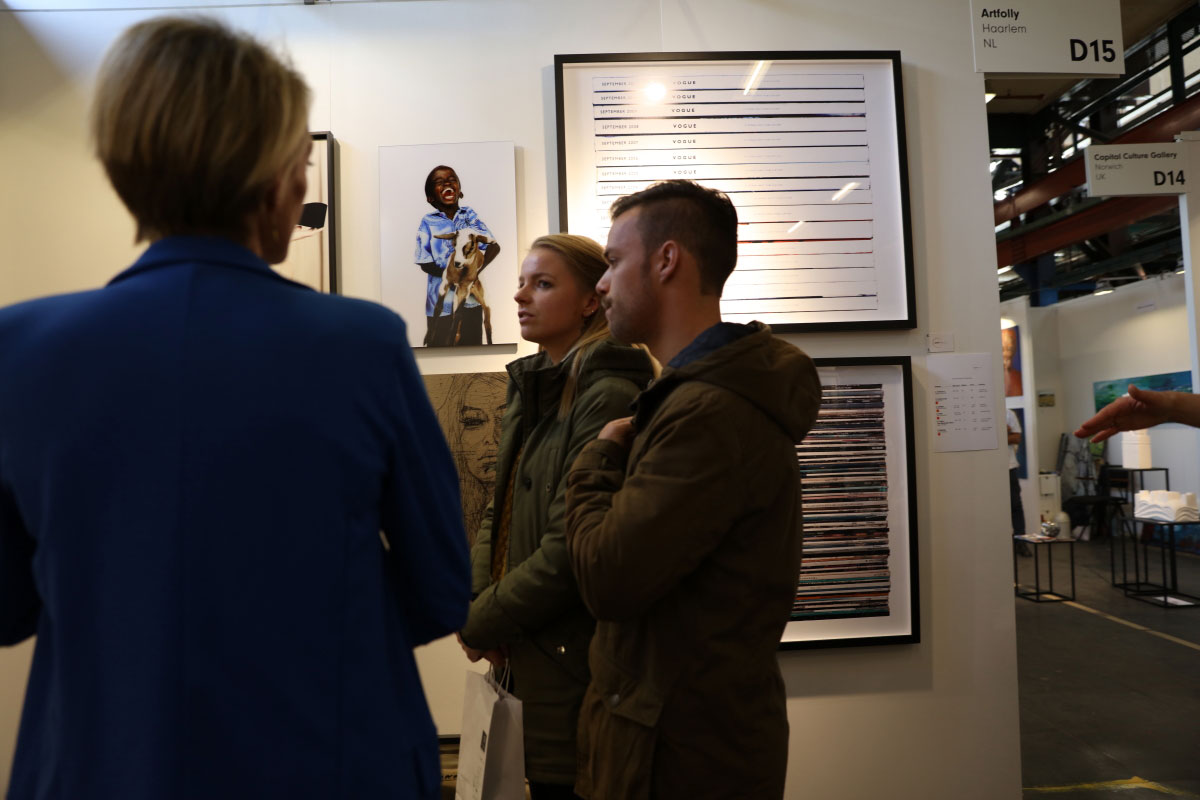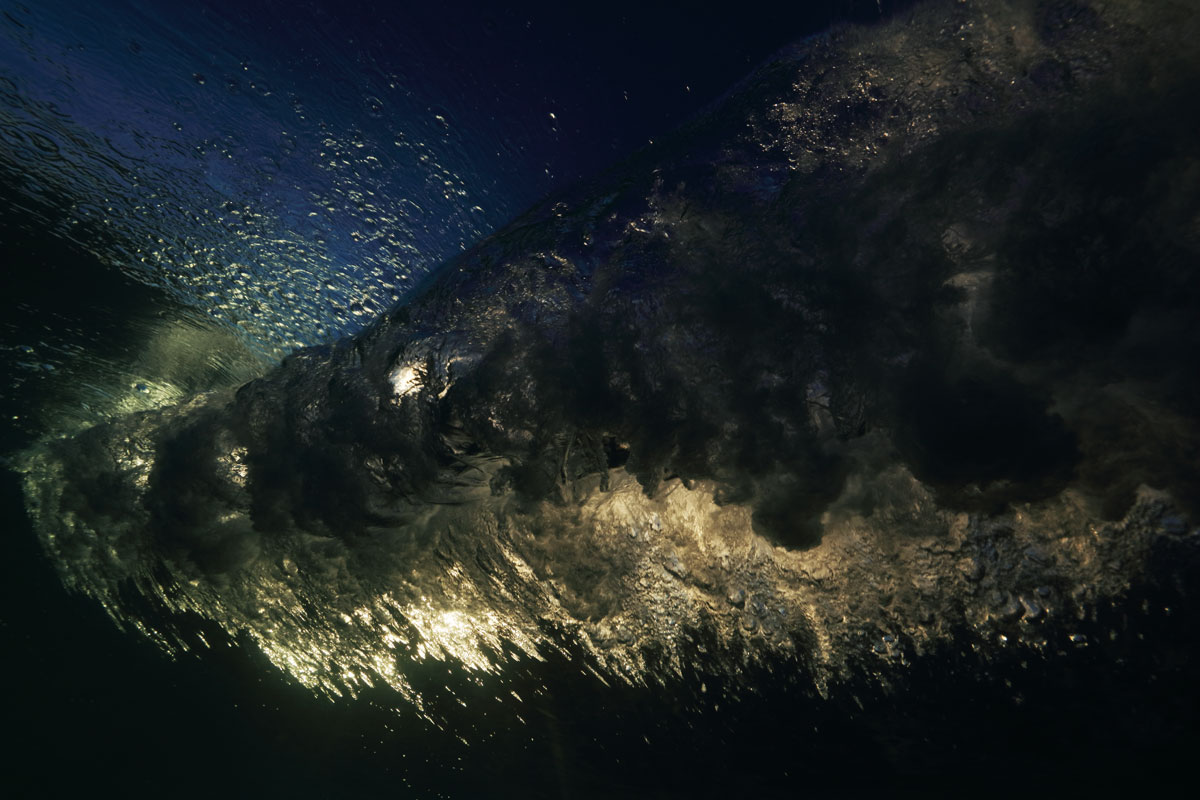2度と同じ波はない
2度と無い時間
海でひつようなこと
行く勇気、やめる勇気
泳力、潜水術、体力、気力
楽しみ、死んでもいい覚悟と準備
心、体の平穏
危ないサメかどうか
はやめに戻る
海や魚への畏敬
全て修行
いらないもの
怯え、考え過ぎ、過信、悔いり、自分の力を知らない
誰かが助けてくれる思い,自分へ嘘をつく
これも修行
己を知る
己と正直に向き合う
掛け値無し
剣道の試合でなく
果たし合いである
しかし征服するのでも
手に入れようとしてはいけない
海はそこにただあるだけで
刻々と変化し闇が迫る
写真がずっと後で教えてくれる事がある
写真もただそのままを、残すだけ
嘘もなくありのまま
昨今その写真に欺瞞や嘘をつかせるのは
人間である
There is never the same wave
Twice and few time
The thing that is necessary in the sea
Courage to go for, courage to stop
Swimming power, art of diving, physical strength, willpower
I am with pleasure, readiness and preparations feeling, state of the body, nothing that may die
Is it a dangerous shark?
Awe to the sea and a fish
All ascetic practices
I do not need it
I tell thought, oneself whom somebody who does not know a scare, an imagination, overconfidence, condolences いり, one’s power helps a lie
This trains itself, too
I know oneself
I face oneself honestly
There is no overcharge
Not a game of the kendo
However, I conquer it
You must not be going to obtain it
The sea changes every moment only by there being merely it there, and darkness approaches
A photograph may teach later all the time, leaving it photograph is plain without a lie
It is a human being to the photograph deception and to let you tell a lie